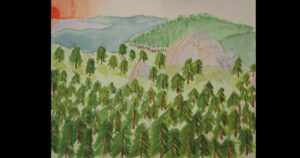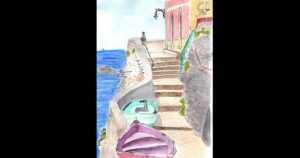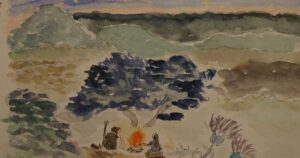高田宏臣
よくわかる土中環境
PARCO出版
この本を読む前は、”土中環境”という馴染みがない言葉に違和感がありましたが、読後、”土中環境”こそ今の世の中で勉強すべき必須の概念だと感じるようになりました。”土中環境”とは、読んで字のごとく土の中の環境のことです。それがなぜ大事なのか…。
著者の高田さんは、2020年に「土中環境 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技(建築資料研究社)」という本を出されていますが、2021年に発生した熱海の土石流と、その土石流を自由研究のテーマとして調べていた小学生からの質問がきっかけで本書を出されました。豊富な写真やイラストを多用しているのが特徴です。
「土地を傷め、災害の起こりやすい国土を作り続けている現代土木建設の問題…」
高田さんは、熱海の土石流が発生した2021年7月3日にSNSにこのような記事を投稿しました(本書の「はじめに」より)。
山や森や川、そして海は、ばらばらに存在しているのではなく、これらが連結してポンプのような役割をはたし、
水や空気を循環しています。人体に例えると、山が心臓で水や空気は血液です。この循環が正常にできていれば、雨水は土中でろ過されて綺麗な水が川にながれこみ、豪雨が降っても川の水は綺麗なままです。
また、高木が根から水を吸い上げる力で地下から水を吸い上げるので、健康な山の土の中はいつでも適度に水が循環して潤っています。このしくみのおかげで、多少雨が降らなくても湧き水が枯れないそうです。
しかし、現在の土木工事はこの”土中環境”の概念がなく、川をコンクリートで固めてただの巨大な水路に変えてしまい、生活圏のいたるところをアスファルトやコンクリートで覆いつくし、水や空気が循環できないようにしてしまいました。
熱海の土石流は、メディアでいわれているような違法盛土の崩壊が主な原因ではなく、この地域の山や川が雨水を循環させる力を失っていたためであり、その根本原因は人間が行った数々の土木工事の影響だと高田さんは指摘しています。土石流の起きた地域にある山の尾根は削られていました。すると、その付近の土は乾き、次第に水が土中にしみ込むことができなくなり、雨水は表面を流れるようになり、泥となって谷底や川底にたまります。泥がたまると循環するしくみは断ち切られて、ますます泥がたまります。盛土の崩壊をきっかけに、たまっていた泥がまとめて流れ出て土石流が発生しました。
この記事を書いているのは2025年ですが、水害のニュースが年々増えて被害も増大していく印象は多くの人が持っているでしょう。本書に書かれている内容のすべてが正しいのか私にはわかりません。しかし、日本の政府や各自治体は各地で起きている水害の原因のひとつの可能性として、一日でも早く”土中環境”のことを検討すべきだと思います。そして、恐れずに”土中環境”にもとづいたインフラ整備に挑戦してほしいです。
本書には、私たちにも身近な暮らしの中でできることが10のアクションとして紹介されています。我が家でも実際にアクション6 「庭に穴や溝を掘る」 を試してみました。通称”グリグリ”として紹介されている長めの貫通ドライバーで地面に穴をぐりぐりあけて、くん炭や落ち葉を入れるというアクションです。秋に庭の何か所かでやってみましたが、翌年、グリグリで穴をあけた近くにある植物は実に元気に成長して、ムラサキシキブは2倍くらいの大きさになり、それまで花がつかなかった移植後のさつきに何輪か花が咲きました。
庭で行った小さなアクションでしたが、土に元気を取り戻す手伝いができて嬉しかったです。また、ちょっとしたことでも”土中環境”が改善したことを実感しました。皆さんにも、できるアクションを実験して効果を実感してほしいです。
※アイキャッチの画像は、本書で紹介されている土中環境のイメージを参考にして描きました。
【広告】
Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。